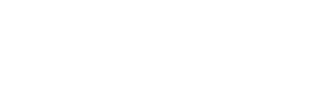血便に冷っとしたら?
突然の血便にびっくりしたことはありませんか。血便、下血の程度はさまざまで、原因もさまざまです。しかし、普段と何か違うことが起こると、不安ですよね。
血便がある場合は、消化管系のどこかに何らかの異常が起きていると考えられます。自己判断せず、お気軽に肛門科や消化器科へご相談ください。
お腹の張りに悩んでいませんか
お腹が張って苦しいという状態を「腹部膨満感」といいます。早食い、ストレス、運動不足、便秘など習慣がきっかけとなって生じることの多い腹部膨満感ですが、消化器系の疾患などが関係していることもあります。お腹が張って苦しい・お腹が痛いなどの症状は、我慢せず医療機関へお気軽にご相談ください。
いぼ痔と切れ痔の予防と治療
いぼ痔や切れ痔は、初期の段階であれば「生活習慣の改善」と「薬」で治療します。痔は、慢性的な排便習慣に原因がありますなので、まずは生活習慣を見直して、良い排便習慣をつくることが大事です。
その状態が保たれていないと、ジオン注射などで痔を治療して治っても、再発する可能性がたかまってしまいます。まずは便秘改善に取り組みましょう。また、お尻の症状は、お薬やジオン注射で治せる早めの段階でご相談ください。
天候の変化で体調不良を起こしていませんか
雨の日や雨が降ってくると、頭痛やめまい、肩こりが起こる人がいます。これは、天候が崩れると気圧が徐々に下がります。気圧の変動は体にとって大きな負担なので、ストレスとして脳に伝わり、自律神経が乱れて、頭痛やめまい、肩こりなどを引き起こしていることなどが考えられます。
早期胃がんは多くが内視鏡治療です!
胃がんと診断されたら、開腹手術と考えている方もまだまだ多いようですが、早期胃がんは多くが内視鏡治療となっています。そんな中、胃がんの早期発見・治療を目的に世田谷区では、40歳以上の区民を対象に胃がん検診を実施していますが、皆様ご存じでしょうか。
50歳以上の方々には従来の胃がん(エックス線)検診に加えて、胃がん(内視鏡)検診の選択肢が追加されています。内視鏡治療ができる状態で胃がんを発見するためにも、胃がん検診を受けましょう。
年に1度の健診・検査を受けていますか
4月から新しい生活がスタートする方も多いのではないでしょうか。新生活の準備に向け、健康診断を久しぶりに受けて再検査となってしまったといった方はいませんか。
病気の予防や早期発見・治療のためには、健診や検査を自覚症状がないうちに受けることが大事です。定期的にご自身の体の状態をチェックし、必要に応じて生活習慣を見直すことで病気の予防ができます。ご自身の健康を守るために、ぜひ年に1度は特定健診やがん検診を受診しましょう。
原因不明の胃の不調に悩んでいませんか?
原因不明の胃の不調で悩んでいる方はいませんか?機能性ディスペシアかもしれません。胃の痛みや胃もたれなどの症状が続いているにもかかわらず精密検査を行っても病変を認めない疾患を「機能性ディスペシア」と言います。機能性ディスペシアも医療機関にて治療が可能です。病変がないからといって、胃の痛みや胃もたれなどの胃の不調感のお悩みを我慢するのではなく、お気軽に医療機関へご相談ください。
腸内フローラとは
腸内フローラという言葉を耳にしたことがある方は多いことと思います。正しい知識をもって腸内フローラの改善に取り組めていますか。腸内フローラを整えるためには、バランスの良い食生活がとても大切です。食物繊維だけ摂取していてもよくありませんし、たんぱく質だけ摂取していてもよくありません。正しい知識をもって腸内に良い食生活を心がけましょう。
大腸内視鏡検査前の注意
大腸内視鏡検査について、検査前の注意事項をまとめてみました。薬の服用、下剤の作り方、検査前日・当日の食事、摂取して良いお飲み物のことなど、当院で検査を受けられる方へお願いしていることとなります。正確な診断を行うため、ご参考いただき、安全で円滑な検査を受けていただきたいと思います。
午後の診療は17:30までに受付をお済ませください
月・火・水・金曜の午後の診療時間は、15:00~18:00となります。受診をご希望の方は、診療時間の30分前までに受付をお済ませください。何卒よろしくお願い申し上げます。
インフルエンザ予防接種を実施中です
10月からインフルエンザ予防接種が開始しました。当院では、世田谷区の高齢者インフルエンザ予防接種も対応しております。東京都内では先月すでに、インフルエンザの流行注意報が発表されております。今年は早めの接種をおすすめしています。
免疫力を高めよう!
過去しばらくの間、インフルエンザの流行がなかったことなどから、今シーズンはインフルエンザ感染症の流行が懸念されています。感染症予防には、自己免疫の強化も重要です!
免疫力を高めるため、適度な運動や、バランスの取れた食事、からだを温めることなどがおすすめです。そして痔の予防にも、これらの習慣は大切となります。冬場は特に、感染症予防、痔の予防を心がけて、健康な体で毎日を過ごしましょう。
「秋バテ」にお気をつけください!
秋がやってきても、夏と同じように疲れや食欲不振が続いていませんか?もしかすると「秋バテ」かもしれません。通常、夏バテは夏の暑さによって体力や食欲が低下し、疲れやだるさなどの不調が出ることを指します。
「秋バテ」は、夏に冷房で冷えたり、冷たい飲食物を摂りすぎたりする生活習慣から、秋になって不調が現れることがあります。秋は行楽シーズンを楽しみたい方も多いことと思います。また、冬の健康を考えるためにも、早めに「秋バテ」を克服しましょう。
腸内環境を整えませんか?
夏休み期間、生活習慣が異なり、食生活が乱れてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。食生活の乱れによって、腸内環境が悪くなり、まず最初に症状として感じるのが「お腹の不調」だと思います。そしてそのお腹の不調は、下痢や便秘さらには、いぼ痔や切れ痔など、お尻のお悩みにもつながります。
お腹がよく痛くなる…
「お腹がよく痛くなる」そんなお悩み我慢していませんか?お腹の痛みはよくある症状です。原因は様々で、腹部の臓器の病気が考えられるものから、精神的なものまであります。診察や検査で異常がなくても痛みが続く場合もあります。
いぼ痔は放置すると危険?
痔には、いぼ痔(痔核)、痔ろう、切れ痔(裂肛)を大きく3種類があります。最も多く方が患っているのは「いぼ痔」で、その「いぼ痔」の中でも内痔核となります。内痔核は、初期の段階では出血はありますが痛みを感じにくいため、放置してしまうことも多いようです。放置するとどんなことが起こる可能性があるかを解説いたします。
痔・がん予防のため暴飲暴食に注意を!
少しずつマスク着用のが緩和される中、会食などのご予定が増えている方が多いのではないでしょうか。健康づくりのため、食事を楽しむことはとても大切です。しかし、痔やがんなどの予防のために、暴飲暴食には気を付けてほしいと思います。
痔の予防になる運動習慣について
日ごとに暖かくなり、春らしい陽気になってきましたね。体を動かしたくなる季節ではないでしょうか。今回は、痔の予防につながる運動についてご紹介したいと思います。これまで痔の予防につながる、食生活や睡眠習慣を中心にご紹介してきましたが、適宜な運動もとても大切です。ぜひごご参考ください。
痔の種類について
痔には、種類があります。日本人にもっとも多いのが「いぼ痔」ですが、その他の痔でお悩みの方もいらっしゃいます。痔の種類によって、対処方法が異なりますので、もしお尻のことで何かお悩みがありましたら、肛門科を受診してもらえらたと思います。あなたの症状に適した治療で、少しでも早くお悩みを改善してもらえたら嬉しい限りです。
自律神経と排便の関わりについて
今年も昨年に続き、新型コロナウイルス感染症の流行の影響によって、オンライン授業やテレワーク、生活リズムが変化した人も多いことと思います。食生活・運動習慣・睡眠時間などの生活のリズムの変化から、自律神経が乱れ、排便習慣や便の状態へも影響が出てきます。そこで、今回は自律神経と排便の関わりについて簡単にご説明いたします。
痔予防として特に冬場気を付けてほしいこと
これからクリスマスや年末年始を迎えるにあたり、ついつい食べすぎ飲みすぎになってしまったい、食生活が乱れてしまうことがあります。食生活の乱れは、便秘や下痢を引き起こす原因となり、おしりの負担、痔の悪化へとつながかねません。
冬に向けての感染症予防について
今冬のインフルエンザについては、新型コロナウイルス感染症との同時流行も懸念されており、日本感染症学会からは積極的なインフルエンザワクチンの接種も推奨されています。世田谷区でも、10月1日より高齢者インフルエンザ予防接種が開始されております。今回は、そのワクチン接種の大切さや注意点などお知らせしたいと思います。
便秘のお悩みも肛門科へご相談ください
快便は、快食、快眠と並び健康的な生活を支える三原則の一つと言われています。便秘になると、単純に便がでないということだけで終わらず、イライラしたり、憂鬱な気分になったりしますよね。また、便秘を対処せず、繰り返したりすることで、痔や大腸の潰瘍、腹膜炎などさまざまな病気を発症することがあります。早めに適切な対処をしてほしいと思います。
夏に気を付けてほしい食中毒について
食中毒は、原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。下痢や腹痛、発熱、はきけなどの症状が出る病気となります。気温が高く、細菌が育ちやすい6月から9月ごろは、細菌による食中毒を発症する方が増える時期でもあります。コロナ対策、熱中症予防、それから食中毒にも注意して夏を乗り切ってほしいと思います。
胃もたれ・胃の痛みとピロリ菌について
ピロリ菌に感染したほとんどの人に胃炎がおこります。ピロリ菌は除菌をしない限り、胃の中にすみ続けて慢性的炎症が続き、胃の粘膜を防御する力が低下していきます。また、慢性的に胃炎が起こることは、日常生活へもさまざまな影響があると思います。胃もたれ・胃の痛みなどでお困りの方お早めにご相談ください。
がん検診は定期的に受診することが大切!
コロナ禍であってもがん検診は定期的に受診することが大切です!当院ホームページの所々でもお伝えしておりますが、現代において、がんは、日本人の2人に1人が生涯のうちに罹患すると言われており、誰でもがんに罹る可能性がある病気です。しかし、医療技術の進歩により、がん検診を定期的に受診し、早期発見・早期治療することにより、多くの方は助かることも分かっています。
男女別、痔になりやすい人
痔には大きくわけて3種類あります。男女や体質、生活習慣などによって、なりやすい痔の種類が異なります。いぼ痔が男女ともに、なりやすい痔ですが、切れ痔においては、女性の方が多いようです。また、痔ろうは、男性に多くみられる痔となります。体質や生活習慣などによって、なりやすい痔が違ってきます。それぞれの特徴や予防法を簡単にご説明したいと思います。
食物繊維とは
皆さまが生活をする中で「現代人は食物繊維の摂取量が不足している」「便秘予防には食物繊維が大事」といったフレーズを、たくさん耳にされていることと思います。そこで今回は、そもそも食物繊維とは何かと、その重要性などについて少し説明したいと思います。
胃がんの危険因子「塩分の摂り過ぎ」について
ダイエットなどの目的から糖質や脂質を控える方は多いようですが、塩分についてはあまり気にしていない、といった方もいらっしゃるように感じています。しかし塩分の摂り過ぎは、胃がんの危険因子や、高血圧になる最大の原因とされています。胃がんの危険因子の1つ塩分について少しご説明したいと思います。
デスクワークによる「いぼ痔」への影響
新型コロナウイルス、オミクロン株による急な感染拡大で、在宅ワークによるデスクワークの時間が長くなっている方、多いようです。昨年10月の記事にも書きましたが、在宅ワーク・デスクワークが続くことで、いぼ痔の症状が悪化することがあります。その理由と、予防について、改めて簡単にご説明いたします。ぜひお役立てください。
痔の予防のためにできる毎日の心がけ!
オミクロン株の感染拡大で外出や移動の機会が減っている方も多いことと思います。そこで痔の予防のため、自宅で今からできる、生活習慣の心がけをご紹介させていただきます。
当たり前のことと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こんな時だからこそ毎日の小さな心がけを大切にしてほしいと思います。ぜひご参考ください。
便潜血検査で陽性だったら!?
大腸がん発見は、便潜血検査で陽性が出たことがきっかけとなることが多いです。しかし、陽性が出た方すべてが、大腸がんと診断されるわけではありません。
陽性が出た場合に「がんだったらどうしよう」と不安になったり、「どうせ痔だろう」と決めつけて精密検査を受けないことがとても危険です。安心して快適な生活を送るために、ぜひ前向きな気持ちで精密検査を受けてほしいと思っています。
大腸がんと間違えやすい「痔」
大腸がんは、日本全国で1年間に約158,000人が診断されています。がんの中で、大腸がんの死亡数は第2位で、女性では第1位になっています(出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計 2020年」)。
こういったデータからも男女ともに注意したい大腸がんですが、大腸がんは「痔」ともっとも間違えやすい病気といわれています。大腸がん早期発見のため、下血や血便があったら精密検査を受けてほしいと思いますし、痔の症状がある方は、しっかりと治療しておくことが大切と考えております。
インフルエンザ予防接種を実施しております
当院ではインフルエンザ予防接種を実施しております。どうぞご利用ください。
※高齢者インフルエンザ予防接種(費用助成)の対象の方は、接種予診票に必要事項をご記入の上、ご来院の際、お持ちください。
胃がん検診の重要性
世田谷区では、40歳以上の世田谷区民の方を対象に胃がん検診を実施しています。その胃がん検診の重要性についてご説明したいと思います。新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、検診を先送りされている方もいらっしゃると思いますが、どうぞ忘れずに、胃がん検診を受けてほしいと思います。
注意してほしいお尻・お腹の症状
お尻・お腹の症状は、痔だけでなくその他さまざまな病気の可能性もあります。「痔だと思い込んでいて検査したらがんだった」などというケースもあり、自己判断はとても危険です。
10~20代で多く発症する病気から、30代以降に発症する病気まで、本当にさまざまです。血便や下血、腹痛や下痢、そしてトイレで「何かおかしい!?」と感じたら、どうぞ放置せずにご相談いただければと思っています。
コロナ禍の生活習慣と痔について
痔の症状は、性別や年齢、季節などに偏りなく発症するお悩みですが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う、外出自粛や在宅ワークが増えたことで、比較的若い年代からのご相談が増えたように思っております。外出自粛や在宅ワークといった生活習慣が痔にどのように影響するか、少し解説させていただきました。ご参考ください。
院内感染対策を実施しております
新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中、当院では十分な感染対策を講じながら、通常通りの診療を行っております。
特定健診、肛門疾患のご相談、痔の治療、胃・大腸内視鏡検査など、皆様の健康を守るため先送りすることなくご相談いただければと思っております。ご来院の際は、感染対策にご理解とご協力のほどお願いいたします。